不動産取引でかつて一般的だった中間省略登記は、法改正によって利用できなくなりました。そこで、中間省略登記の新たな方法として考案されたのが、新中間省略登記とも呼ばれる三為契約です。
本記事では、三為契約が生まれた背景やメリット・デメリット、従来の中間省略登記との違い、利用する際に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
もくじ
三為契約は新中間省略登記として生まれた方法

スムーズな不動産取引と費用の節約のために、以前は「中間省略登記」という方法が使われていました。しかし、問題点もあったため、法改正によって現在は禁止されています。そして、代わりの取引方法として登場したのが「三為契約」です。
まずは、三為契約の基本的な内容を、中間省略登記も含めて詳しくみていきましょう。
効率的に不動産取引をするための中間省略登記
中間省略登記とは、複数回の所有権移転がある不動産取引で途中の登記を省略して、最初の所有者から最後の所有者へ直接移転したように登記する方法です。例えば、AからBへ、BからCへと売買された場合、本来はA→B、B→Cと2回の登記が必要ですが、中間省略登記ではA→Cと1回で済ませます。登記回数を減らすことで取引の手間と費用を軽減できる点が、中間省略登記のメリットです。
問題点から従来の中間省略登記を禁止
不動産取引で重宝されていた中間省略登記ですが、権利移転の経緯が正確に登記に反映されないという問題点がありました。そこで、2005年の改正不動産登記法により、従来の方法での中間省略登記が禁止されます。
AからB、そしてBからCへと所有権を移した場合、権利移転の流れをすべて登記簿にも記録すべきです。しかし、中間省略登記ではAから直接Cへと移転登記が行われていました。これは、権利移転の事実を忠実に記録するという、法務局が重視する原則に反しています。法改正では、登記原因証明情報の添付が登記申請時に必須とされました。結果的に、A→Cという直接の移転登記は現在では不可能です。
新しい登記方法として三為契約が誕生
中間省略登記が禁止されたことにより登場したのが、中間者を中心に締結する三為契約です。三為契約では、中間者である不動産会社が、売主と買主との間で2つの契約を結びます。
まず、売主Aと中間者Bの間で売買契約を結ぶ際、買主Cに所有権が直接移転される特約をつけていることがポイントです。一方で買主とは、第三者である買主に売主の所有物を売却する契約を結びます。
つまり、所有権が中間者Bに移ることがないため、そもそもA→B、B→Cの移転登記は不要です。中間者Bは、あくまでも第三者のための契約を締結することから、三為契約と呼ばれています。
三為契約と中間省略登記の違い
従来の中間省略登記と新しく登場した三為契約は、所有権移転のプロセスを簡略化する点では共通しています。両者の大きな違いは、所有権移転の流れが正しく登記されているかどうかです。
中間省略登記では、中間者を省略して最終的な買主だけを登記します。しかし、実際の所有権移転の流れをつかめなくなる点が大きな問題でした。
一方の三為契約では、実際の所有権が売主から買主に直接移転します。改正後に考案された三為契約は、法務省にも公認されている取引方法です。
三為契約を結ぶメリット

三為契約のメリットは、登記手続きが簡素化されることだけではありません。物件の不具合があった場合の責任を追及しやすくなる、融資が通りやすくなるといったさまざまな恩恵を受けられます。
三為取引の4つのメリットを、それぞれ詳しくみていきましょう。
取引にかかる手間とコストを削減できる
登記回数が少ないことから、中間省略登記と同様に取引の手間とコストを抑えられる点が三為契約のメリットです。また、売買契約という点では、中間者は一旦物件を購入するため、仲介手数料も発生しません。
つまり、売主の売買契約は、単純に不動産会社への売却です。一方の買主は不動産会社から物件を購入するだけのため、双方がシンプルな契約内容となります。
契約不適合責任を追及できる
物件を購入した買主は、契約内容にない不具合があった場合に責任を追及しやすくなります。物件の売主はあくまでも不動産会社のため、宅建業法に基づいて責任を追及できます。
一般的な売買契約で不具合が発生した場合は、売主個人への責任追及が必要です。しかし、個人で保証できる範囲には限度があるため、契約不適合責任の範囲が制限されたり免状されたりするケースもあります。一方で、宅建業法に縛られた不動産会社が売主の場合、契約不適合責任を免れることは困難です。三為契約であれば、買主と売主の双方が安心して取引できます。
融資を受けやすくなる
売主が不動産会社となる三為契約には、融資の承認を得やすいメリットがあります。仲介取引や個人間取引では、価格の妥当性の判断が難しく、融資を受けられないケースも少なくありません。しかし、不動産会社が売主になることで売買金額の妥当性が担保されるため、融資が通りやすくなります。
金融機関との関係が深い不動産会社であれば、自己資金が少ない場合でも金融機関の承認を得やすくなるかもしれません。
責任の所在が明確
中間者の権利移転を省略する中間省略登記とは異なり、三為契約では権利移転と売買契約の当事者が明確になっています。所有権の移転先と物件の売却相手が契約書に明記されるため、誰に責任のある取引なのかが、売主、中間者、買主の3者間で明確です。
とくに、中間者である不動産業者は、宅地建物取引業者として大きな責任を負います。個人間の取引にはない安心感が得られるのは、金額の大きな不動産取引では大きなメリットです。
三為契約のデメリットと注意点
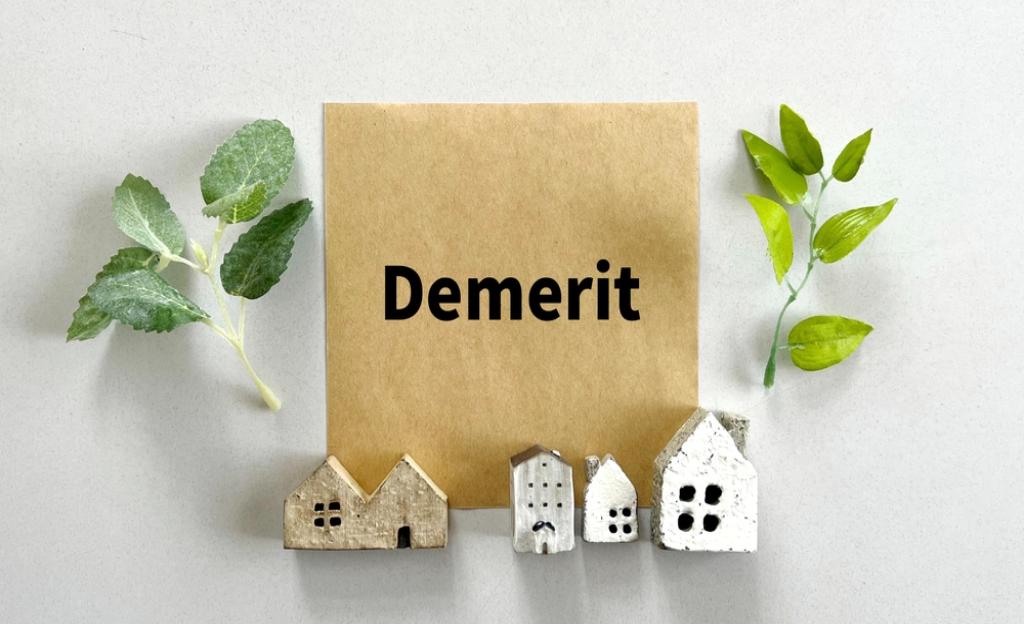
万能にも思える三為契約ですが、実はデメリットや注意点もあります。売買契約の中心が、専門家である不動産会社になるためです。
一般的に売主と買主は個人のため、経験や知識量では不動産会社にかないません。不利な条件での取引にならないよう、デメリットと注意点を把握しておきましょう。
取引内容や金額が不透明でわかりにくい
三為契約の内容は基本的に中間者がまとめるため、取引の条件や金額がわかりにくい点がデメリットです。また、売主と買主が直接顔を合わせることがないため、不動産会社だけが得をする状況に陥るおそれもあります。
ただし、売主と買主が、それぞれ納得のいく条件であれば問題ありません。売買金額を中心に、契約内容を事前によく確認しておきましょう。
相場に対して不利な条件になるおそれがある
三為契約では、売却金額、購入金額ともに相場よりも悪い金額設定となるケースがあります。中間者である不動産会社は売買代金の差額が利益となるため、購入はより安く、売却はより高く設定されがちなためです。
極端な価格差がある場合は売主、買主にとってデメリットが大きくなってしまいますが、不動産会社も利益を得る必要があるため、契約の構造上やむを得ない部分もあります。メリットの部分も含めて、しっかりと検討することが大切です。
トラブルが発生しやすい
三為契約で不動産取引をする際、トラブルには十分注意する必要があります。三者がそれぞれ別の契約を結ぶため、誰かがリスクを負う契約内容となっているケースがあるためです。
所有権は売主から買主に直接移転するものの、売買代金は不動産会社を通じてやり取りします。売主への入金、手付金の取り扱い、買主の支払い日といった細かい部分の認識を合わせておかないと、思わぬトラブルにつながりかねません。三為契約を結ぶ場合は、契約内容の細部も十分に確認しておきましょう。
【まとめ】三為契約は内容をよく理解して利用することが重要

三為契約は、不動産取引を効率化する便利な方法です。また、法の抜け穴ではなく、法務省も公認しています。しかし、基本的な仕組みはもちろん、契約内容をしっかりと理解しておかないと損をするケースもあるため注意が必要です。
また、三為契約にはデメリットや注意点もあります。契約内容を理解していないことでトラブルに発展してしまっては、本来契約を簡素化するはずが本末転倒になりかねません。三為契約を利用する際は、メリットとデメリットを十分に検討して納得のいく取引をしてください。
イー・トラストではここまでご紹介した不動産取引についてや、中古マンション経営、投資・収益物件のご案内・投資のコンサルティングのほか、不動産売却の査定・買取りなどに関しても幅広くご案内をしております。
また、仲介だけではなく、マンション管理や賃貸管理、建物修繕等をグループ会社で一括して行い、多様なニーズにお応えしておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。




